【南島研】創立40周年シンポジウムを開催しました
南島研
南島文化研究所では、創立40周年シンポジウムを開催しました。学内、学外から多くの方々に参加いただき、質疑応答も活発に行われました。
【南島文化研究所創立40周年シンポジウム】
テーマ:再び、「シマ」とはなにかを問う
日時:2018年12月22日(土)13:00~17:00
会場:沖縄国際大学 3号館203教室
【プログラム】
司会:岩田直子(南島文化研究所所員)
開会の辞:前津 榮健(沖縄国際大学学長)
趣旨説明:崎浜 靖(南島文化研究所所長)
パート1:考古学からシマを探る
考古学からみるシマ
上原靜(南島文化研究所所員/第11・13代南島文化研究所所長)
宮城弘樹(南島文化研究所所員)
パート2:歴史学からシマを探る
近世の間切と村のたたずまい
田名真之(沖縄県立博物館・美術館館長/第12代南島文化研究所所長)
深澤秋人(南島文化研究所所員)
パート3:社会学からシマを探る
沖縄の都市と「シマ」
波平勇夫(沖縄国際大学名誉教授/第5代南島文化研究所所長)
澤田佳世(南島文化研究所所員)
パート4:祭りからシマを探る
祭祀芸能を継承するエネルギー
狩俣恵一(南島文化研究所所員/第11代南島文化研究所副所長)
西岡敏(南島文化研究所副所長)
コメンテーター:来間泰男(沖縄国際大学名誉教授/第6代南島文化研究所所長)
総合討論司会:小川護(南島文化研究所所員/10代南島文化研究所所長)














《参加者の感想》アンケートより一部抜粋
・「シマ」を取り上げ、「シマ」の文化、社会構造など学際的に多様な切り口があることを再認識することができた。
・4者とも大変よかったです。波平先生の模合の件は、沖縄以外の事例(韓国、中国、インドネシア)と比較してくださり、大変興味をひかれました。
・間切、シマ、村のおこりや使い方の変遷等について理解が深まった。
・先生方のご講演から、積み上げてこられた学識の幅、深さを感じ、感銘を受けました。学問の専門分化が進み、細かい仕事となりがちな昨今ですが、先輩方を見習って。大きな仕事につながっていくように日々努めたいと感じました。
・本土出身です。私が住んできた場所は行政単位としての町内会(自治会)の表面的なつながりはありました。しかし、沖縄に住んでみると地域の人同士の間で何かよくわからないけれど、それ以上の精神的なつながりがあるように感じていました。これは「シマ」意識によるものなのかなと思いました。
・八重山の民謡などは士族たちの知識が入っている。当時の新しい知識をシマにおろし、影響を与える存在であったことがわかった。「芸能は今を生きる我々と関わる物語である」という言葉が印象に残りました。
・稲作の伝来と普及、農耕時代について、上原氏と来間氏の稲作社会を問い、グスク時代の役割についての話が印象に残りました。
・来間先生のコメントは非常に興味深い内容でした。狩俣先生の唄はいいアクセントになりました。手話のサービスもとても素晴らしいと思います。
多くの皆様のご参加、誠にありがとうございました。
【南島文化研究所創立40周年シンポジウム】
テーマ:再び、「シマ」とはなにかを問う
日時:2018年12月22日(土)13:00~17:00
会場:沖縄国際大学 3号館203教室
【プログラム】
司会:岩田直子(南島文化研究所所員)
開会の辞:前津 榮健(沖縄国際大学学長)
趣旨説明:崎浜 靖(南島文化研究所所長)
パート1:考古学からシマを探る
考古学からみるシマ
上原靜(南島文化研究所所員/第11・13代南島文化研究所所長)
宮城弘樹(南島文化研究所所員)
パート2:歴史学からシマを探る
近世の間切と村のたたずまい
田名真之(沖縄県立博物館・美術館館長/第12代南島文化研究所所長)
深澤秋人(南島文化研究所所員)
パート3:社会学からシマを探る
沖縄の都市と「シマ」
波平勇夫(沖縄国際大学名誉教授/第5代南島文化研究所所長)
澤田佳世(南島文化研究所所員)
パート4:祭りからシマを探る
祭祀芸能を継承するエネルギー
狩俣恵一(南島文化研究所所員/第11代南島文化研究所副所長)
西岡敏(南島文化研究所副所長)
コメンテーター:来間泰男(沖縄国際大学名誉教授/第6代南島文化研究所所長)
総合討論司会:小川護(南島文化研究所所員/10代南島文化研究所所長)




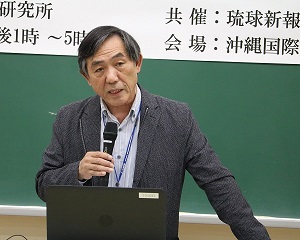

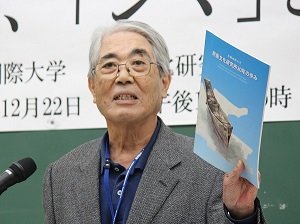







《参加者の感想》アンケートより一部抜粋
・「シマ」を取り上げ、「シマ」の文化、社会構造など学際的に多様な切り口があることを再認識することができた。
・4者とも大変よかったです。波平先生の模合の件は、沖縄以外の事例(韓国、中国、インドネシア)と比較してくださり、大変興味をひかれました。
・間切、シマ、村のおこりや使い方の変遷等について理解が深まった。
・先生方のご講演から、積み上げてこられた学識の幅、深さを感じ、感銘を受けました。学問の専門分化が進み、細かい仕事となりがちな昨今ですが、先輩方を見習って。大きな仕事につながっていくように日々努めたいと感じました。
・本土出身です。私が住んできた場所は行政単位としての町内会(自治会)の表面的なつながりはありました。しかし、沖縄に住んでみると地域の人同士の間で何かよくわからないけれど、それ以上の精神的なつながりがあるように感じていました。これは「シマ」意識によるものなのかなと思いました。
・八重山の民謡などは士族たちの知識が入っている。当時の新しい知識をシマにおろし、影響を与える存在であったことがわかった。「芸能は今を生きる我々と関わる物語である」という言葉が印象に残りました。
・稲作の伝来と普及、農耕時代について、上原氏と来間氏の稲作社会を問い、グスク時代の役割についての話が印象に残りました。
・来間先生のコメントは非常に興味深い内容でした。狩俣先生の唄はいいアクセントになりました。手話のサービスもとても素晴らしいと思います。
多くの皆様のご参加、誠にありがとうございました。


