【南島研】第219回 シマ研究会(オンライン)を開催しました
南島研
南島文化研究所は、第219回 シマ研究会をオンラインで開催しました。
県内、県外からオンラインにて多くの方々にご参加いただきました。
【第219回 シマ研究会】
■テーマ:
「社会の変化と共同労働―波照間島におけるサトウキビ収穫の事例―」
■報告者
阿利 よし乃(南島文化研究所 所員)
■コメンテーター
小川 護(南島文化研究所 所員)
■司会
岩田 直子(南島文化研究所 所長)
■報告概要
本報告では2018年時点の波照間島におけるサトウキビ収穫ユイマールの事例を取り上げる。波照間島では昭和30年代まで稲作が行われていた。しかし、その稲作は雨量によって収穫量が左右される不安定なものであった。人びとは生活の安定を求めて1962年に中型の製糖工場を導入し、サトウキビ作へと農業形態を転換させた。その際に組織されたのがサトウキビ収穫のための共同労働、賃金制のユイマールである。
賃金制ユイマールが始まって50年以上が経った今日、島の人口は減少し、農家の戸数も半減した。その現状において、人びとのユイマールに対する意見は一様ではない。波照間島の農家は社会の変化にどのように対応しているのだろうか。具体的な事例をあげて農家の生き方を捉えてみたい。

写真1:阿利 よし乃(南島文化研究所 所員)

写真2:小川 護(南島文化研究所 所員)

写真3:岩田 直子(南島文化研究所 所長)

写真4:オンライン開催の様子
《参加者の感想》アンケートより一部抜粋
・波照間島の黒糖業についての貴重な学習機会となりました。
・サトウキビ産業の状況、この後の課題について学ばせていただきました。ありがとうございます。
県内、県外からオンラインにて多くの方々にご参加いただきました。
【第219回 シマ研究会】
■テーマ:
「社会の変化と共同労働―波照間島におけるサトウキビ収穫の事例―」
■報告者
阿利 よし乃(南島文化研究所 所員)
■コメンテーター
小川 護(南島文化研究所 所員)
■司会
岩田 直子(南島文化研究所 所長)
■報告概要
本報告では2018年時点の波照間島におけるサトウキビ収穫ユイマールの事例を取り上げる。波照間島では昭和30年代まで稲作が行われていた。しかし、その稲作は雨量によって収穫量が左右される不安定なものであった。人びとは生活の安定を求めて1962年に中型の製糖工場を導入し、サトウキビ作へと農業形態を転換させた。その際に組織されたのがサトウキビ収穫のための共同労働、賃金制のユイマールである。
賃金制ユイマールが始まって50年以上が経った今日、島の人口は減少し、農家の戸数も半減した。その現状において、人びとのユイマールに対する意見は一様ではない。波照間島の農家は社会の変化にどのように対応しているのだろうか。具体的な事例をあげて農家の生き方を捉えてみたい。

写真1:阿利 よし乃(南島文化研究所 所員)
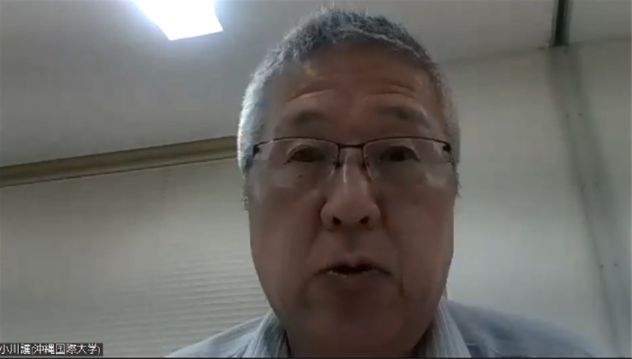
写真2:小川 護(南島文化研究所 所員)

写真3:岩田 直子(南島文化研究所 所長)

写真4:オンライン開催の様子
《参加者の感想》アンケートより一部抜粋
・波照間島の黒糖業についての貴重な学習機会となりました。
・サトウキビ産業の状況、この後の課題について学ばせていただきました。ありがとうございます。


