【社会文化学科】宮城弘樹先生が第46回沖縄研究奨励賞を受賞!
社会文化学科
総合文化学部教授の宮城弘樹先生が第46回沖縄研究奨励賞(人文科学部門)を受賞されました。
沖縄研究奨励賞は沖縄の地域振興に貢献する人材を発掘し育成することを目的としています。
宮城先生はこれまで琉球列島先史時代の終末期、グスク時代、琉球王国時代に関する考古学研究の整理など精力的かつ意欲的に研究に取り組み、今後の活躍が大いに期待されています。
今回の受賞について、喜びの声などをお聞きしました。
■今回の受賞について
若手研究者を奨励するということも一つありますが、今回の受賞はとても栄誉なことですし、素直にありがたいと思っています。
■先生の研究分野について
考古学は人の歴史の研究です。人類の歴史の中でも文字が登場する以前の歴史を先史時代、文字が登場する時代は歴史時代といいます。
考古学者の多くは先史時代の研究、歴史学者は歴史時代など、時代によって研究の住み分けがあります。
私の場合は、歴史学が対象とする琉球王国時代に対して、砦(グスク・お城)やお墓、焼き物の生産地などの遺跡から出土された実物資料から、琉球王国時代の文化がどのようなものであったのか紐解くことを研究しております。
例えば、琉球王国時代の県内遺跡から出土したお墓の中から指輪が出てきました。同時代である江戸時代の文化には簪(かんざし)はありますが指輪はなく、映像作品でも分かりますが、お姫様や花魁(おいらん)は基本的に指輪はしないんですよ。
琉球王国時代の遺跡で見つけた実物資料が後世の人が語っている内容と違う状態で見つかったり、独自の文化を築いていることが分かるなど、遺跡から発掘された実物資料が語ってくれる面白さがあります。
また、数は少ないですが、遺跡から髷(まげ)が出てくる事例もあります。その結われた毛束をX線CTスキャンで断面を観察することで、琉球王国時代の髪結い文化や手仕事がアーカイブされていることも感じます。
琉球舞踊の髪結いの先生に見ていただくと、「これはかたかしらだね」とか「これは女性のいなぐからじだね」とか、画像資料のねじりかたから琉球王国時代や近代のものなどの髪型を推察し、復元していくということもやっています。
実物資料の細かいところなど沢山の資料を集めて、これまで光の当たってこなかったような、わからなかったようなことに考古学の視点でアプローチできる「歴史時代の研究」というものに関心をもっています。
■先生が研究を行うにあたって、遺跡の場所などいくつか決めて調査されているのでしょうか。
私が直接調査するというようなことはほとんどなくて、すでにもう発掘調査されているデータを探してきます。
(研究室にある発掘調査の報告書など)発掘調査の事例があって資料自体は博物館や市町村の行政機関に文化財として保管されていますので、そういうものを調べて、再調査させてもらうというのがほとんどですね。
■先生はいつごろから考古学に興味をもたれたのでしょうか。
中学生の時から考古学が好きで、その当時に学芸員さんと知り合いになり、その人をきっかけに学芸員という仕事を知りました。
母校の沖縄国際大学でも博物館学芸員のカリキュラムが登場した頃に入学したのもきっかけです。
卒業論文のテーマは「先史時代の終末」で、最後の狩猟採集民と農耕民がどう付き合っていたのか、王国時代まで物々交換や貨幣の取引があったのか色々考えていました。
卒業後は、世界遺産を登録するために必要な学芸員を探していた今帰仁村の行政職として入職しました。
遺跡の整備や管理、2002年に登録したあとは観光地として土地利用をするための発掘調査を行いました。
今帰仁村での発掘調査はとても面白く、先史時代から歴史時代にはまっていくきっかけになりました。
■現在の研究を今後どのように展開していくか。
お墓などの遺跡発掘調査をきっかけに、古い時代の精神世界に関心があります。
また、琉球王国時代のグスクについて単に按司が住まう砦としてではなく、ウタキの場としていつから参拝が始まったのかなど多義的なアプローチから考えたり、グスクとウタキの関連性にも興味があります。
グスク参拝についても、沖縄の門中による今帰仁ヌブイやアガリマーイなど、いつ整備されていつ展開したなども歴史的に考えたり、お墓からさかのぼって古琉球時代まで考えていけたらと思います。
■沖縄研究奨励賞は沖縄の研究者にとってどのような意義があると思われますか。
沖縄は二百の島々がまとまっており、それぞれの島で華やかな時代や、歴史的に困難な時代にユニークなタレントが登場することを魅力的に感じます。
島々によって、その人物による求心力が生まれる瞬間がいくつもあります。
そういった沖縄を研究対象にこれまで受賞されている先生方はビッグネームばかりで、そこに届くように改めて研鑽していきたいです。
また、学生とも一緒に遺跡を学ぶ楽しさなどを共有して、学生からも多くの刺激をもらっていますので、そういうものを活かしていきたいと思っております。
■取材後記
今回の取材で、これまで宮城先生が研究されてきた考古学について分かりやすく教えていただきました。
沖縄という土地で暮らしてきた人々の歴史や様々な文化について、これからも先生の研究を通して紐解いていただけるのではと思いました。
第46回沖縄研究奨励賞の贈呈式は、令和7年1月22日(水)に行われる予定です。
宮城先生、改めて沖縄研究奨励賞受賞おめでとうございます。
公益財団法人沖縄協会
https://www.okinawakyoukai.jp/pages/49/

沖縄研究奨励賞を受賞した宮城弘樹先生(総合文化学部社会文化学科教授)
沖縄研究奨励賞は沖縄の地域振興に貢献する人材を発掘し育成することを目的としています。
宮城先生はこれまで琉球列島先史時代の終末期、グスク時代、琉球王国時代に関する考古学研究の整理など精力的かつ意欲的に研究に取り組み、今後の活躍が大いに期待されています。
今回の受賞について、喜びの声などをお聞きしました。
■今回の受賞について
若手研究者を奨励するということも一つありますが、今回の受賞はとても栄誉なことですし、素直にありがたいと思っています。
■先生の研究分野について
考古学は人の歴史の研究です。人類の歴史の中でも文字が登場する以前の歴史を先史時代、文字が登場する時代は歴史時代といいます。
考古学者の多くは先史時代の研究、歴史学者は歴史時代など、時代によって研究の住み分けがあります。
私の場合は、歴史学が対象とする琉球王国時代に対して、砦(グスク・お城)やお墓、焼き物の生産地などの遺跡から出土された実物資料から、琉球王国時代の文化がどのようなものであったのか紐解くことを研究しております。
例えば、琉球王国時代の県内遺跡から出土したお墓の中から指輪が出てきました。同時代である江戸時代の文化には簪(かんざし)はありますが指輪はなく、映像作品でも分かりますが、お姫様や花魁(おいらん)は基本的に指輪はしないんですよ。
琉球王国時代の遺跡で見つけた実物資料が後世の人が語っている内容と違う状態で見つかったり、独自の文化を築いていることが分かるなど、遺跡から発掘された実物資料が語ってくれる面白さがあります。
また、数は少ないですが、遺跡から髷(まげ)が出てくる事例もあります。その結われた毛束をX線CTスキャンで断面を観察することで、琉球王国時代の髪結い文化や手仕事がアーカイブされていることも感じます。
琉球舞踊の髪結いの先生に見ていただくと、「これはかたかしらだね」とか「これは女性のいなぐからじだね」とか、画像資料のねじりかたから琉球王国時代や近代のものなどの髪型を推察し、復元していくということもやっています。
実物資料の細かいところなど沢山の資料を集めて、これまで光の当たってこなかったような、わからなかったようなことに考古学の視点でアプローチできる「歴史時代の研究」というものに関心をもっています。
■先生が研究を行うにあたって、遺跡の場所などいくつか決めて調査されているのでしょうか。
私が直接調査するというようなことはほとんどなくて、すでにもう発掘調査されているデータを探してきます。
(研究室にある発掘調査の報告書など)発掘調査の事例があって資料自体は博物館や市町村の行政機関に文化財として保管されていますので、そういうものを調べて、再調査させてもらうというのがほとんどですね。
■先生はいつごろから考古学に興味をもたれたのでしょうか。
中学生の時から考古学が好きで、その当時に学芸員さんと知り合いになり、その人をきっかけに学芸員という仕事を知りました。
母校の沖縄国際大学でも博物館学芸員のカリキュラムが登場した頃に入学したのもきっかけです。
卒業論文のテーマは「先史時代の終末」で、最後の狩猟採集民と農耕民がどう付き合っていたのか、王国時代まで物々交換や貨幣の取引があったのか色々考えていました。
卒業後は、世界遺産を登録するために必要な学芸員を探していた今帰仁村の行政職として入職しました。
遺跡の整備や管理、2002年に登録したあとは観光地として土地利用をするための発掘調査を行いました。
今帰仁村での発掘調査はとても面白く、先史時代から歴史時代にはまっていくきっかけになりました。
■現在の研究を今後どのように展開していくか。
お墓などの遺跡発掘調査をきっかけに、古い時代の精神世界に関心があります。
また、琉球王国時代のグスクについて単に按司が住まう砦としてではなく、ウタキの場としていつから参拝が始まったのかなど多義的なアプローチから考えたり、グスクとウタキの関連性にも興味があります。
グスク参拝についても、沖縄の門中による今帰仁ヌブイやアガリマーイなど、いつ整備されていつ展開したなども歴史的に考えたり、お墓からさかのぼって古琉球時代まで考えていけたらと思います。
■沖縄研究奨励賞は沖縄の研究者にとってどのような意義があると思われますか。
沖縄は二百の島々がまとまっており、それぞれの島で華やかな時代や、歴史的に困難な時代にユニークなタレントが登場することを魅力的に感じます。
島々によって、その人物による求心力が生まれる瞬間がいくつもあります。
そういった沖縄を研究対象にこれまで受賞されている先生方はビッグネームばかりで、そこに届くように改めて研鑽していきたいです。
また、学生とも一緒に遺跡を学ぶ楽しさなどを共有して、学生からも多くの刺激をもらっていますので、そういうものを活かしていきたいと思っております。
■取材後記
今回の取材で、これまで宮城先生が研究されてきた考古学について分かりやすく教えていただきました。
沖縄という土地で暮らしてきた人々の歴史や様々な文化について、これからも先生の研究を通して紐解いていただけるのではと思いました。
第46回沖縄研究奨励賞の贈呈式は、令和7年1月22日(水)に行われる予定です。
宮城先生、改めて沖縄研究奨励賞受賞おめでとうございます。
公益財団法人沖縄協会
https://www.okinawakyoukai.jp/pages/49/
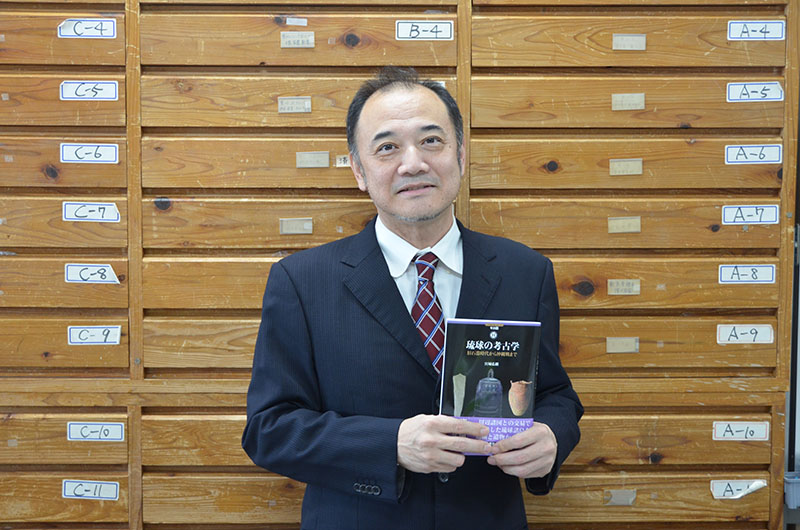
沖縄研究奨励賞を受賞した宮城弘樹先生(総合文化学部社会文化学科教授)


