| 文字サイズ |
|---|
沖縄国際大学トップ > 学部・学科トップ > 総合文化学部 > 総合文化学部教員一覧 > 石垣 直
石垣 直(ISHIGAKI, Naoki)
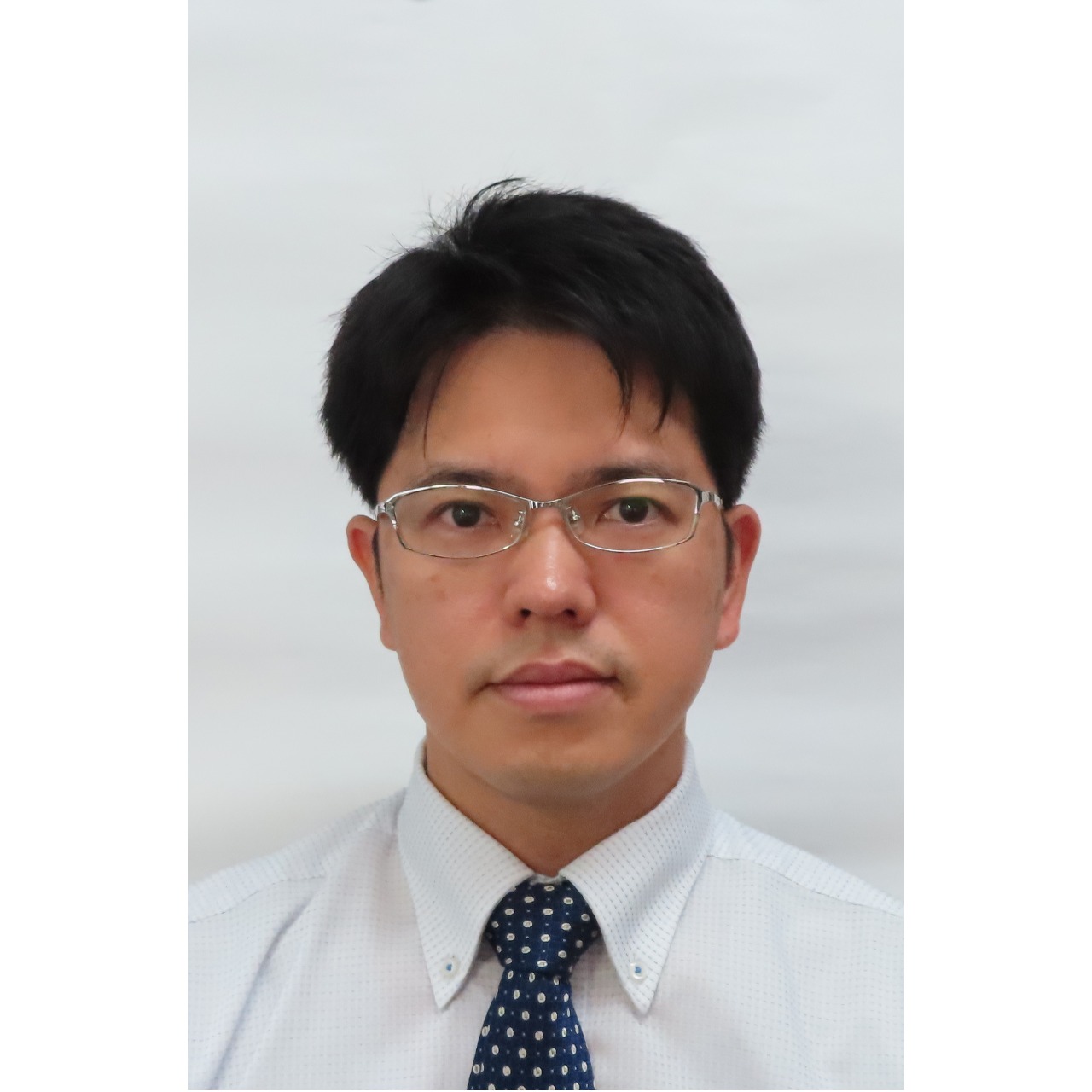
所属: 総合文化学部 社会文化学科
職階: 教授
担当科目:沖縄文化入門、文化人類学概論、アジア文化概論、
演習Ⅰ・Ⅱ、他
職階: 教授
担当科目:沖縄文化入門、文化人類学概論、アジア文化概論、
演習Ⅰ・Ⅱ、他
| 主要学歴 | 東京都立大学大学院 社会科学研究科 社会人類学専攻 博士課程(単位取得退学) |
|---|---|
| 学位 | 博士 |
| 研究分野 | 文化人類学、台湾地域研究、沖縄地域研究 |
| 所属学会・協会等 | 日本文化人類学会、日本台湾学会、沖縄民俗学会、沖縄文化協会 |
| 主要な社会的活動 | 沖縄民俗学会・運営委員、那覇日体親善協会・理事 |
| E-mail・ホームページ等 | メールアドレス:nishigaki@okiu.ac.jp 研究者情報&研究業績:http://researchmap.jp/read0124251/ |
教育活動等
| 【教育活動等】 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | 主な教育活動 | 摘要 |
| 2010 年 4 月~ | 文化人類学概論 | ・学科 必修科目(後期) ・講義内容:親族、贈与交換、儀礼、象徴・認識・コミュニケーション、世界観・宗教など、生活にかかわる諸トピックを文化人類学的な視点で理解する作法について講義。 ・登録者数:約 100 人。 |
| 2010 年 4 月~ | アジア文化概論 | ・学科 選択必修科目(前期) ・講義内容:沖縄を取り巻く周辺地域、具体的には中国、韓国、日本、台湾、東南アジア、オセアニアの概要・歴史・文化に関する基礎的理解を深めることを目指した講義。 ・登録者数:約 60 人。 |
| 2011 年 9 月~ | アジア社会文化論Ⅰ | ・学科 選択科目(後期) ・講義内容:中国について、基本データ、歴史、言語、親族・人間関係、思想・宗教、現代社会などのトピックを取り上げて講義。 ・登録者数:約 50 人。 |
| 2017 年 9 月~ | 琉球アジア文化論 | ・学科 選択科目(後期) ・講義内容:沖縄の文化(歴史、親族、葬墓制、年中行事、人生儀礼、オナリ神信仰、物質文化、食文化)東アジア的な視野での理解のための講義。 ・登録者数:約 40 人 |
| 2010 年 4 月~ | 領域演習(2年) | ・学科 必修科目(前期) ・演習内容:大学での学びについてガイダンス、文献検索、レジュメ作法、レポート作法、論文作法、フィールドワーク作法、ミニ・フィールドワーク体験、小グループでのテーマ選び/文献調査/プレゼンテーション ・登録者数:約 30 人。 |
| 2015 年 4 月~ | 沖縄文化入門 | ・学科 必修科目(前期) ・講義内容:民俗学担当の教員とともに、オムニバス形式で沖縄文化の基礎的理解のための講義。個人的な担当は、地理・歴史的位置性、親族・門中、祖先祭祀・葬墓制、女性の霊的優位、年中行事、人生儀礼。 ・登録者数:約 100 人 |
| 2010年4月~ | 多民族論 | ・共通科目(国際理解科目群 前期/後期) ・講義内容:「民族」・「国民」概念の歴史的な成立、世界各地の民族紛争(アフリカ、中東、アジア、ヨーロッパ)、先住民族運動、多文化主義の歴史と現状について講義。 ・登録者数:約 100 人 |
| 2010 年 4 月~ | 演習Ⅰ(3年) | ・学科 必修科目(通年) ・演習内容:毎年テーマを選び、基礎文献・関連文献を輪読した上で、夏休みを中心に 1 週間程度の調査実習を行い、年度末には実習報告書(『みんぞく』)を作成。 ・登録者数:約 15 人。 ※本ゼミでは、「アジアのなかの沖縄」を考える契機として、台北の史跡・博物館・大学などを訪問する「海外研習」も実施。 |
| 2010 年 4 月~ | 演習Ⅱ(4年) | ・学科 必修科目(通年) ・演習内容:卒業論文作成を目的とし、文献研究、フィールドワーク、論文作成に関する指導。履修学生が扱って卒業論文のテーマは、沖縄の民俗・文化、言語復興、沖縄戦・平和教育、基地問題、周辺アジア諸国と沖縄との比較研究、観光、工芸品など。 ・登録者数:約 15 人。 |
| 2014 年 4 月~ | 東アジア文化人類学特論ⅠA/ⅠB | ・大学院科目(地域文化専攻 民俗文化領域) ・講義内容:Ⅰでは中華圏の親族・社会組織を中心に、Ⅱでは中華圏の思想・宗教を中心に講義・輪読・討議。 |
| 2016 年 4 月~ | 南島民俗文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ | ・大学院科目(地域文化専攻 民俗文化領域) ・演習内容:沖縄の民俗文化、フィールドワーク論、関連文献輪読、論文作成指導。 |
| 【作成した教科書・教材・参考書】 | ||
| 年月日 | 分野 | 書名 |
| 2016年3月 | 沖縄研究 | ・沖縄国際大学宜野湾の会(編)『大学的沖縄ガイド』、昭和堂 (分担執筆) |
| 2018 年2月 | 先住民族 | ・深山直子/丸山淳子/木村真希子(編)『先住民からみる現代世界:わたしたちの〈あたりまえ〉に挑む』、昭和堂 (分担執筆) |
| 【学生支援活動】 | ||
| 年月日 | 分野 | 内容 |
| 2010 年 4 月~ | 学習支援 | ・オフィスアワー:木曜日・3限をオフィスアワーに設定し、学生指導。 |
| 2010 年 4 月~ | キャリア支援 | ・領域演習(2年生)その他のゼミで、受講生に対し、人生設計、大学生活、就職活動などについて説明・指導。国内/海外留学やインターンシップも推奨。 |
| 【学外での教育活動】 | ||
| 年月日 | 種類 | 内容 |
| 2011 年 11 月 | 学生団体での講演 | ・沖縄県内のインカレ団体である「学生観光振興プロジェクト」の学生たちに対し、台湾の歴史と現状&沖縄とのつながりについて講義。 |
| 2015 年 11 月~ | 那覇日台親善協会 | ・台湾と沖縄の交流を推進する民間団体「那覇日台親善協会」で学術部会理事として運営に参加。各種交流イベント、講演会などを実施。 |
| 2016 年 10 月 | 高校生向け出張講座 | ・台湾への修学旅行を実施している球陽高校の学生向けに、台湾の概要・歴史・文化に関する講義。 |
| 2017 年 7 月 | 商工会議所での出張講座 | ・台湾視察を予定している南風原町商工会会員向けに台湾の概要・歴史・文化に関する講義を行った。 |
| 【教育改善活動(FDなど)】 | ||
| 年月日 | 種類 | 内容 |
| 2010 年 4 月~ | 授業評価アンケート | ・毎学期、講義科目で「授業評価アンケート」を実施し、その結果を講義様式の改善などに役立てている。(e.g. プロジェクター利用、デジタルファイル用法、映像教材利用、etc.) |
| 2010 年 4 月~ | レスポンス・ぺーバー | ・大学が義務付ける「授業評価アンケート」とは別に、自身が担当するすべての講義・演習において、「レスポンス・ペーパー」(出席票プラスコメント・質問・要望欄)を毎回配布し、学生たちの興味・理解度チェック、講義手法の改善に活用。 |
| 【授業での新型コロナ対応】 | ||
| 年月日 | 内容 | |
| 2020年度 | ・Google Classroomなどを活用してのオンライン講義(レジュメ、資料、講義音声の提供)を実施。 | |
| 2021年度 | ・Microsoft Temasを活用してのオンライン講義(レジュメ&資料の提供、ビデオ会議形式での講義)を実施。 |
研究活動等(著書・論文等)
【著書(共著)】
・『現代台湾を生きる原住民:ブヌンの土地と権利回復運動の人類学』(単著、風響社、2011 年)
【論文】
・"Multi-layered 'colonial experience': collisions, contacts, and re-encounters of the Bunun with 'Japan'," Mio, Yuko (ed.) Memories of Japan Empire: Comparison of the Colonial and Decolonization Experiences in Taiwan and Nan'yō Guntō. (2021, London & New York: Routledge)
・戦後沖縄における釈奠復興:『具志堅以徳収集文書』他にみる台北市孔廟からの影響(『南島文化』43号、沖縄国際大学南島文化研究所、2020年)
・現代台湾における原住民族教育政策:族語教育、部落学校、実験教育の事例を中心に(『台湾原住民研究』24、2020年)
・戦後沖縄における久米・至聖廟再建と中華民国:1975年前後の協力・寄贈品とその政治・文化的背景への注目から」(『南島文化』42号、沖縄国際大学南島文化研究所、2020年)
・琉球・沖縄における釈奠の歴史と現在:久米・至聖廟の事例を中心に(『南島文化』41号、沖縄国際大学南島文化研究所、2019年)
・現代台湾における原住民母語復興(3):ブヌンの事例からみる教育現場の現状と課題(『南島文化』40 号、沖縄国際大学南島文化研究所、2018 年)
・近代国家の成立と「先住民族」:台湾と沖縄の歴史と現状(深山直子/丸山淳子/木村真希子(編)『先住民からみる現代世界:わたしたちの〈あたりまえ〉に挑む』、昭和堂、2018 年)
・現代台湾における原住民族語復興への取り組み:その歴史的経緯・実践と沖縄「しまくとぅば復興」への提言(沖縄国際大学公開講座委員会(編)『しまくとぅばルネサンス』 〔沖縄国際大学公開講座 26〕東洋企画、2017 年)
・Return to the Homeland: Land Claims and Historical Changes in the Relationship between the Bunun and their Land"(中央研究院民族學研究所/順益台灣原住民博物館(編)『民族、地理與發展:人地關係研究的跨學科交會』、〔順益台灣原住民博物館20周年紀念叢書2〕順益台湾原住民博物館、2017 年)
・交錯する植民地経験:台湾原住民・ブヌンと「日本」の衝突・接触・邂逅(三尾裕子・遠藤央・植野弘子(編)『帝国日本の記憶:台湾・旧南洋群島における外来政権の重層化と脱植民地化』、慶應義塾大学出版会、2016 年)
・現代台湾における原住民母語復興(2):教科書・教材内容の検討(『南島文化』38号、沖縄国際大学南島文化研究所、2016 年)
・「祭り・年中行事にみる沖縄文化の歴史と現在:ハーリー、綱引き、エイサー」(沖縄国際大学宜野湾の会(編)『大学的沖縄ガイド』、昭和堂、2016 年)
・現代台湾における原住民母語復興(1):諸政策の歴史的展開と現在(『南島文化』37号、沖縄国際大学南島文化研究所、2015 年)
・土地をめぐる複ゲーム状況:台湾・ブヌン社会の事例から(杉島敬志編『複ゲーム状況の人類学:東南アジアにおける構想と実践』、風響社、2014 年)
・現代台湾における原住民族運動:ナショナル/グローバルな潮流とローカル社会の現実(日本順益台湾原住民研究会編『台湾原住民研究の射程:接合される過去と現在』、風響社、2014 年)
・先住民族運動と琉球・沖縄:歴史的経緯と様々な取り組み(『世変わりの後で復帰40年を考える』〔沖縄国際大学公開講座 22〕、東洋企画、2013 年)
・現代台湾社会をめぐる「求心力・遠心力」と原住民:ブヌンの事例を中心とした初歩的検討(沼崎一郎・佐藤幸人編『交錯する台湾社会』、アジア経済研究所、2012 年)
・ブヌン研究史における馬淵東一の位置:特徴・問題点・可能性(笠原政治編『馬淵東一と台湾原住民族研究』、風響社、2010 年)
・現代台湾における原住民族母語教育:その歴史と現状(第32回南島文化市民講座「“しまくとぅば”の未来:少数派言語とその活性化」、沖縄国際大学南島文化研究所、2010 年)
・土地所有をめぐる現実:台湾・ブヌン社会における保留地継承・分配制度の現代的諸相(『アジア・アフリカ言語文化研究』77 号、東京外国語大学、2009 年)
・現代ブヌン社会における高齢者セイフティー・ネットワーク(『民俗文化研究』10 号、2009 年)
・現代台湾の多文化主義と先住権の行方:〈原住民族〉による土地をめぐる権利回復運動の事例から(『日本台湾学会報』9号、2007 年)
・高齢者と生きがい:川崎市川崎区における沖縄出身者の事例から(『高齢化社会から熟年社会へ:都市形成過程における高齢者の多様化とそのセーフティ・ネットワークの構築』(平成18年度傾斜的研究費 (都市形成に関わる研究) 研究成果報告書、2007 年)
・現代台湾における〈原住民族〉の位置づけ:「原住民族自治区法」草案をめぐって(『社会人類学年報』32 号、2006 年)
・「部落地圖」調査之省思:以布農族之内本鹿調査爲例(『東台灣研究』10 号、中文、2005 年)
・イエとクラン:台湾・ブヌン社会の「クラン」概念再考(小池誠編『アジアの家社会』(アジア遊学 No.74)、勉誠出版、2005 年)
・内本鹿への旅:〈尋根〉の人類学にむけて(『台湾原住民研究』8号、2004 年)
・沖縄・金武町における門中の現在と人類学:屋嘉・前田門中の事例から(『民俗文化研究』4号、2003 年)
・故郷への帰還:台湾先住民・ブヌン社会における〈部落地図〉作成運動と想像力(『社会人類学年報』29 号、2003 年)
・台湾ブヌンの現代的婚姻:“home-land Bunun”のその後(『台湾原住民研究』5号、2001 年)
【書評その他】
・松田京子(著)『帝国の思考:日本「帝国」と台湾原住民』(『台湾原住民研究』18 号、2015 年)
・黄應貴(著)『「文明』之路』(『台湾原住民研究』17 号、2014 年)
・先住権(含 先住権原)〔事典項目〕(国立民族学博物館編、『世界民族百科事典』、丸善、2014 年)
・林淑美(編著)『現代オーストロネシア語族と華人:口述歴史:台湾を事例として』(『台湾原住民研究』16 号、2013 年)
・Book Review: WAKABAYASHI, Masahiro 2008 The“Republic of China”and the Politics of Taiwanization: The Changing Identity of Taiwan in Postwar East Asia.(China Information 25(1), March, 2011)
・湯浅浩史(著)『瀬川孝吉 台灣原住民族影像誌 布農族篇』(『台湾原住民研究』14 号、2010 年)
・夷將・拔路兒等(編)『台灣原住民族運動史料彙編』(上・下)』(『台湾原住民研究』13 号、2009 年)
・先住民のうた・こころ 台湾・ブヌン1~3(『婦人之友』7~9月号、2009 年)
・『現代台湾を生きる原住民:ブヌンの土地と権利回復運動の人類学』(単著、風響社、2011 年)
【論文】
・"Multi-layered 'colonial experience': collisions, contacts, and re-encounters of the Bunun with 'Japan'," Mio, Yuko (ed.) Memories of Japan Empire: Comparison of the Colonial and Decolonization Experiences in Taiwan and Nan'yō Guntō. (2021, London & New York: Routledge)
・戦後沖縄における釈奠復興:『具志堅以徳収集文書』他にみる台北市孔廟からの影響(『南島文化』43号、沖縄国際大学南島文化研究所、2020年)
・現代台湾における原住民族教育政策:族語教育、部落学校、実験教育の事例を中心に(『台湾原住民研究』24、2020年)
・戦後沖縄における久米・至聖廟再建と中華民国:1975年前後の協力・寄贈品とその政治・文化的背景への注目から」(『南島文化』42号、沖縄国際大学南島文化研究所、2020年)
・琉球・沖縄における釈奠の歴史と現在:久米・至聖廟の事例を中心に(『南島文化』41号、沖縄国際大学南島文化研究所、2019年)
・現代台湾における原住民母語復興(3):ブヌンの事例からみる教育現場の現状と課題(『南島文化』40 号、沖縄国際大学南島文化研究所、2018 年)
・近代国家の成立と「先住民族」:台湾と沖縄の歴史と現状(深山直子/丸山淳子/木村真希子(編)『先住民からみる現代世界:わたしたちの〈あたりまえ〉に挑む』、昭和堂、2018 年)
・現代台湾における原住民族語復興への取り組み:その歴史的経緯・実践と沖縄「しまくとぅば復興」への提言(沖縄国際大学公開講座委員会(編)『しまくとぅばルネサンス』 〔沖縄国際大学公開講座 26〕東洋企画、2017 年)
・Return to the Homeland: Land Claims and Historical Changes in the Relationship between the Bunun and their Land"(中央研究院民族學研究所/順益台灣原住民博物館(編)『民族、地理與發展:人地關係研究的跨學科交會』、〔順益台灣原住民博物館20周年紀念叢書2〕順益台湾原住民博物館、2017 年)
・交錯する植民地経験:台湾原住民・ブヌンと「日本」の衝突・接触・邂逅(三尾裕子・遠藤央・植野弘子(編)『帝国日本の記憶:台湾・旧南洋群島における外来政権の重層化と脱植民地化』、慶應義塾大学出版会、2016 年)
・現代台湾における原住民母語復興(2):教科書・教材内容の検討(『南島文化』38号、沖縄国際大学南島文化研究所、2016 年)
・「祭り・年中行事にみる沖縄文化の歴史と現在:ハーリー、綱引き、エイサー」(沖縄国際大学宜野湾の会(編)『大学的沖縄ガイド』、昭和堂、2016 年)
・現代台湾における原住民母語復興(1):諸政策の歴史的展開と現在(『南島文化』37号、沖縄国際大学南島文化研究所、2015 年)
・土地をめぐる複ゲーム状況:台湾・ブヌン社会の事例から(杉島敬志編『複ゲーム状況の人類学:東南アジアにおける構想と実践』、風響社、2014 年)
・現代台湾における原住民族運動:ナショナル/グローバルな潮流とローカル社会の現実(日本順益台湾原住民研究会編『台湾原住民研究の射程:接合される過去と現在』、風響社、2014 年)
・先住民族運動と琉球・沖縄:歴史的経緯と様々な取り組み(『世変わりの後で復帰40年を考える』〔沖縄国際大学公開講座 22〕、東洋企画、2013 年)
・現代台湾社会をめぐる「求心力・遠心力」と原住民:ブヌンの事例を中心とした初歩的検討(沼崎一郎・佐藤幸人編『交錯する台湾社会』、アジア経済研究所、2012 年)
・ブヌン研究史における馬淵東一の位置:特徴・問題点・可能性(笠原政治編『馬淵東一と台湾原住民族研究』、風響社、2010 年)
・現代台湾における原住民族母語教育:その歴史と現状(第32回南島文化市民講座「“しまくとぅば”の未来:少数派言語とその活性化」、沖縄国際大学南島文化研究所、2010 年)
・土地所有をめぐる現実:台湾・ブヌン社会における保留地継承・分配制度の現代的諸相(『アジア・アフリカ言語文化研究』77 号、東京外国語大学、2009 年)
・現代ブヌン社会における高齢者セイフティー・ネットワーク(『民俗文化研究』10 号、2009 年)
・現代台湾の多文化主義と先住権の行方:〈原住民族〉による土地をめぐる権利回復運動の事例から(『日本台湾学会報』9号、2007 年)
・高齢者と生きがい:川崎市川崎区における沖縄出身者の事例から(『高齢化社会から熟年社会へ:都市形成過程における高齢者の多様化とそのセーフティ・ネットワークの構築』(平成18年度傾斜的研究費 (都市形成に関わる研究) 研究成果報告書、2007 年)
・現代台湾における〈原住民族〉の位置づけ:「原住民族自治区法」草案をめぐって(『社会人類学年報』32 号、2006 年)
・「部落地圖」調査之省思:以布農族之内本鹿調査爲例(『東台灣研究』10 号、中文、2005 年)
・イエとクラン:台湾・ブヌン社会の「クラン」概念再考(小池誠編『アジアの家社会』(アジア遊学 No.74)、勉誠出版、2005 年)
・内本鹿への旅:〈尋根〉の人類学にむけて(『台湾原住民研究』8号、2004 年)
・沖縄・金武町における門中の現在と人類学:屋嘉・前田門中の事例から(『民俗文化研究』4号、2003 年)
・故郷への帰還:台湾先住民・ブヌン社会における〈部落地図〉作成運動と想像力(『社会人類学年報』29 号、2003 年)
・台湾ブヌンの現代的婚姻:“home-land Bunun”のその後(『台湾原住民研究』5号、2001 年)
【書評その他】
・松田京子(著)『帝国の思考:日本「帝国」と台湾原住民』(『台湾原住民研究』18 号、2015 年)
・黄應貴(著)『「文明』之路』(『台湾原住民研究』17 号、2014 年)
・先住権(含 先住権原)〔事典項目〕(国立民族学博物館編、『世界民族百科事典』、丸善、2014 年)
・林淑美(編著)『現代オーストロネシア語族と華人:口述歴史:台湾を事例として』(『台湾原住民研究』16 号、2013 年)
・Book Review: WAKABAYASHI, Masahiro 2008 The“Republic of China”and the Politics of Taiwanization: The Changing Identity of Taiwan in Postwar East Asia.(China Information 25(1), March, 2011)
・湯浅浩史(著)『瀬川孝吉 台灣原住民族影像誌 布農族篇』(『台湾原住民研究』14 号、2010 年)
・夷將・拔路兒等(編)『台灣原住民族運動史料彙編』(上・下)』(『台湾原住民研究』13 号、2009 年)
・先住民のうた・こころ 台湾・ブヌン1~3(『婦人之友』7~9月号、2009 年)
2021年9月23日現在

