| 文字サイズ |
|---|
沖縄国際大学トップ > 学部・学科トップ > 総合文化学部 > 総合文化学部教員一覧 > 村上 陽子
村上 陽子(MURAKAMI,Yoko)
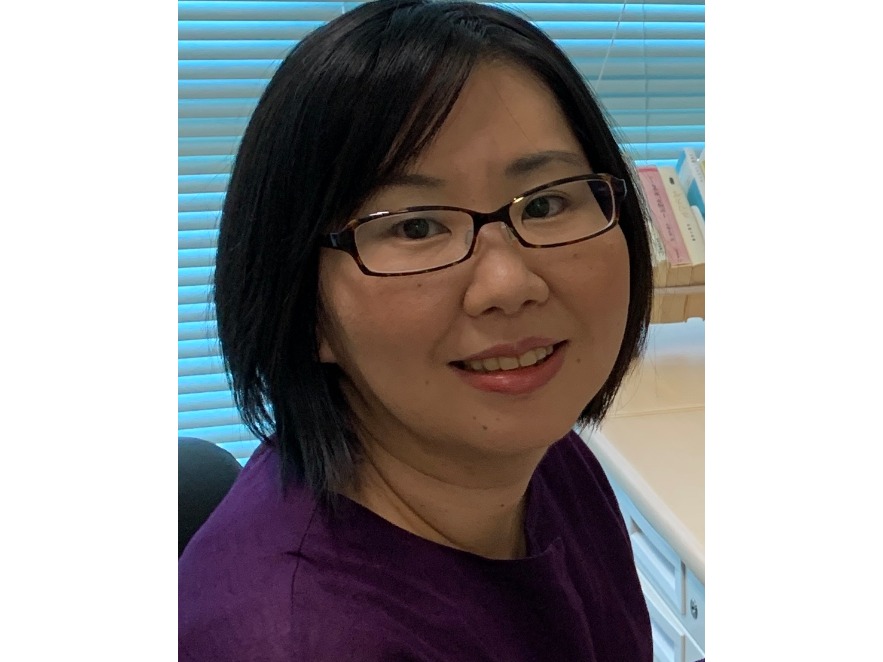
所属: 総合文化学部 日本文化学科
職階: 教授
担当科目:
卒業論文Ⅰ・Ⅱ、ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、
日本近代文学史Ⅰ・Ⅱ、日本文学を読むⅢ・Ⅳ、
現代文学理論I・Ⅱ、日本言語文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ(大学院)、
日本近現代文学特論ⅡA・ⅡB(大学院)
職階: 教授
担当科目:
卒業論文Ⅰ・Ⅱ、ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、
日本近代文学史Ⅰ・Ⅱ、日本文学を読むⅢ・Ⅳ、
現代文学理論I・Ⅱ、日本言語文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ(大学院)、
日本近現代文学特論ⅡA・ⅡB(大学院)
| 主要学歴 | 琉球大学大学院人文社会科学研究科国際言語文化専攻(修士課程) 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻(博士課程) |
|---|---|
| 学位 | 博士(学術) |
| 研究分野 | 沖縄・日本近現代文学 |
| 所属学会・協会等 | 日本近代文学会、昭和文学会、日本文学協会、日本社会文学会、原爆文学研究会 |
| 主要な社会的活動 | 日本社会文学会理事(2019年4月〜) 琉球大学びぶりお文学賞小説部門選考委員(2018年〜) おきなわ文学賞小説部門選考委員(2021年〜) 『社会文学』57号編集委員長(2022年) 『昭和文学』編集委員(2022年〜) |
| 趣味 | 手紙を書くこと |
| E-mail・ホームページ等 | y.murakami@okiu.ac.jp https://researchmap.jp/sun-drops22/ |
教育活動等
| 【教育活動等】 | ||
|---|---|---|
| 年月日 | 主な教育活動 | 摘要 |
| 2016年4月〜 | 現代文学理論Ⅰ・Ⅱ | 3〜4年次対象専門科目、講義、前期・後期、各2単位、各15回、授業登録者数100名前後。文学理論を学び、理論を用いたテクスト読解を行っている。 |
| 2021年4月〜 | 日本近代文学史Ⅰ | 1〜4年次対象専門科目、講義、前期、2単位、16回(テストを含む)、授業登録者数100名前後。近代文学の流れを追うのみではなく実際の作品に触れることを重視し、短編小説の分析を行っている |
| 2016年9月〜 | 日本近代文学史Ⅱ | 1〜4年次対象専門科目、講義、後期、2単位、16回(テストを含む)、授業登録者数100名前後。近代文学の流れを追うのみではなく実際の作品に触れることを重視し、短編小説の分析や中・長編小説の一部抜粋の分析、映像資料の活用などを取り入れている。 |
| 2021年4月〜 | 日本文学を読むⅢ・Ⅳ | 2〜4年次対象専門科目、講義、前期・後期、各2単位、各15回、授業登録者数60名前後。日本文学を読むⅢでは夏目漱石「こころ」を通して長編小説の読解を行い、日本文学を読むⅣでは現代女性文学を扱っている。 |
| 2016年4月〜 | ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 3〜4年次対象専門科目、演習、前期・後期、各2単位、各15回、授業登録者数各学年10~13名程度。まずテーマに沿って選定されたテクストを分析し、卒業論文執筆のための基礎的な力を養うため、文献収集、先行研究の読み込み、発表資料の作成を行う。また、他の受講生のテーマにも関心を持ち、グループディスカッションを通して問題を深められるよう指導を行っている。 |
| 2017年4月〜 | 卒業論文Ⅰ・Ⅱ | 4年次対象専門科目、演習、前期・後期、各2単位、各15回、授業登録者数11~13名。各自が選択したテーマに基づき、テクスト分析を中心とした卒業論文の執筆に取り組んでいく。発表資料に基づくグループディスカッションを毎回実施する。 |
| 学生支援活動 | ||
| 2016年4月〜 | 文芸部顧問 | 文芸部の学生の創作に対するアドバイスや講評を行うとともに、県内文学賞への積極的な投稿を促している。 |
研究活動等(著書・論文等)
【主要論文】
「「日本人」の変容の可能性に向けて—大江健三郎『沖縄ノート』を読む』、『ユリイカ』2023年7月臨時増刊号
「〈沖縄〉を教える—沖縄県の国語科副読本をめぐって」、『昭和文学研究』85集、2022年9月
「イクサの記憶を生きる身体―崎山多美「うんじゅが、ナサキ」論」、『沖縄国際大学日本語日本文学研究』 25巻1号、2021年2月
ほか
【著書(共著含む)】
飯田祐子・小平麻衣子編『ジェンダー×小説ガイドブック 日本近現代文学の読み方』ひつじ書房、2023年5月
又吉栄喜・山里勝己・大城貞俊・崎浜慎編『沖縄を求めて沖縄を生きる―大城立裕追悼論集』インパクト出版会、2022年5月
千葉一幹・西川史子・松田浩・中丸貴史編著『日本文学の見取り図―宮崎駿から古事記まで』2022年2月
紅野謙介・内藤千珠子・成田龍一編著『〈戦後文学〉の現在形』平凡社、2020年10月
坪井秀人編『戦後日本を読みかえる5 東アジアの中の戦後日本』臨川書店、2018年8月
村上陽子『出来事の残響―原爆文学と沖縄文学』インパクト出版会、2015年7月
ほか
「「日本人」の変容の可能性に向けて—大江健三郎『沖縄ノート』を読む』、『ユリイカ』2023年7月臨時増刊号
「〈沖縄〉を教える—沖縄県の国語科副読本をめぐって」、『昭和文学研究』85集、2022年9月
「イクサの記憶を生きる身体―崎山多美「うんじゅが、ナサキ」論」、『沖縄国際大学日本語日本文学研究』 25巻1号、2021年2月
ほか
【著書(共著含む)】
飯田祐子・小平麻衣子編『ジェンダー×小説ガイドブック 日本近現代文学の読み方』ひつじ書房、2023年5月
又吉栄喜・山里勝己・大城貞俊・崎浜慎編『沖縄を求めて沖縄を生きる―大城立裕追悼論集』インパクト出版会、2022年5月
千葉一幹・西川史子・松田浩・中丸貴史編著『日本文学の見取り図―宮崎駿から古事記まで』2022年2月
紅野謙介・内藤千珠子・成田龍一編著『〈戦後文学〉の現在形』平凡社、2020年10月
坪井秀人編『戦後日本を読みかえる5 東アジアの中の戦後日本』臨川書店、2018年8月
村上陽子『出来事の残響―原爆文学と沖縄文学』インパクト出版会、2015年7月
ほか
2024年4月5日現在

