【「多文化を学ぶ」ってどういうことなの? コース担当の先生に聞いてみました!】
入試お得情報!
日本文化学科には、「日本文化コース」「琉球文化コース」「多文化間コミュニケーションコース」の3コースが設置され、1・2年生の間は、3つのコースの基礎科目をしっかり学び、3年生になると、3つのコースから1つを選んで、研究室に所属して、さらに専門的な知識を身に着けていきます。
「多文化間コミュニケーションコース」はいまから10年ほど前に設置された新しいコースです。受験生向けに、2年生の仲よし3人組が、コース担当の3人の先生(奥山先生、安先生、劉先生)の研究室に行って取材をしてきてくれましたので、こちらでレポートを紹介します。
どんな楽しい学びが詰まっているか、大学選びのぜひ参考にしてみてくださいね。

ーーー「多文化間コミュニケーション」ってあまり聞かない言葉ですが、どんな意味の言葉なんですか?
奥山先生 「“異”文化コミュニケーション」はよく聞く言葉ですね。日本文化学科では文化と文化の“異なり”だけに注目するのではないこと、様々な文化同士の関わりについて考えること、この二つを意識して「多文化間コミュニケーション」という言葉を使っています。
ーーーそうなんですね。多文化間コミュニケーションコースではどんなことを学べるんですか?
奥山先生 そうですね、日文で学べる多文化間コミュニケーションに関わる分野は本当に幅広いのですが、今回は多文化共生について話してみましょう。

ーーー「多文化共生」について、受験生にもわかりやすく教えてください!
奥山先生 多文化共生は、多様な背景を持つ人々がお互いに尊重し合いながら一緒に社会の中で生きていくこと、と言えます。そのためには、自文化への理解、他文化への理解、コミュニケーションの知識やスキル、など必要なことが様々あります。国境を越えた人の行き来が普通になっている中、とても大切な考え方になっています。
ーーー具体的にどんなところが魅力なのでしょうか?
安先生 普段当たり前すぎて意識していない自文化や、様々な他文化を理解していくことは単純に楽しいですよ。色々な人と関わったり、色々なところに行ったりしながら学べますし。そうやって、様々な人との関わりや社会のことを学び考えるることで、共生する力を身に付けられます。
ーーー外国人との関り方について学べるということですか?
劉先生 外国人に限りませんよね。世代、ジェンダー、地域、隣にいる人は自分とは異なる背景を持っていますよ。ですから、多文化共生の知識やスキルを身に付けられると、将来何をするにしても自分の生活や人生を豊かにしてくれると思いますよ。
ーーー最後に受験生へのメッセージをお願いします。
奥山先生 留学生と関わったり海外に行ってみたりして、様々な文化を体験してみましょう。講義で学ぶ専門的な知識を踏まえてそうした体験を繰り返すことで、人や社会への理解がぐっと深まります。「多文化」について学んで、自分のこと、他者のこと、社会のこと、を深く理解していくのは、とても知的な刺激に満ちた経験ですよ。一歩踏み出す勇気を持ってみましょう。
安先生 「アンニョンハセヨ!最近、日本では様々な国の文化が人気です。皆さんの好きなものは何ですか?「好きこそものの上手なれ」という言葉があります。皆さんの好きなものを一緒に掘り下げてみませんか?きっと今まで気づかなかった風景が広がるはずです。多文化コミュニケーションコースで皆さんを待っています!」
劉先生 料理(ラフテー)、建築(赤瓦の屋根)、芸能(古典音楽)、祭り(旧正月)など、さまざまな面で中国文化が根付いており、それが沖縄独自の文化として発展しています。このような多文化共生の環境は、沖縄の魅力の一つであり、異なる文化を比較することで、自分の文化への理解がグッと深まります。言語や文学は、その文化を映し出す鏡。さあ、一緒に多文化の世界へ飛び込んでみませんか?沖国大日文で新しい発見が待っています!

ーーー先生方、本日はありがとうございました。多文化間コミュニケーションコースのことがよくわかりました。受験生の皆さんもぜひ日本文化学科で一緒に多文化について学びましょう!
「多文化間コミュニケーションコース」はいまから10年ほど前に設置された新しいコースです。受験生向けに、2年生の仲よし3人組が、コース担当の3人の先生(奥山先生、安先生、劉先生)の研究室に行って取材をしてきてくれましたので、こちらでレポートを紹介します。
どんな楽しい学びが詰まっているか、大学選びのぜひ参考にしてみてくださいね。

ーーー「多文化間コミュニケーション」ってあまり聞かない言葉ですが、どんな意味の言葉なんですか?
奥山先生 「“異”文化コミュニケーション」はよく聞く言葉ですね。日本文化学科では文化と文化の“異なり”だけに注目するのではないこと、様々な文化同士の関わりについて考えること、この二つを意識して「多文化間コミュニケーション」という言葉を使っています。
ーーーそうなんですね。多文化間コミュニケーションコースではどんなことを学べるんですか?
奥山先生 そうですね、日文で学べる多文化間コミュニケーションに関わる分野は本当に幅広いのですが、今回は多文化共生について話してみましょう。

ーーー「多文化共生」について、受験生にもわかりやすく教えてください!
奥山先生 多文化共生は、多様な背景を持つ人々がお互いに尊重し合いながら一緒に社会の中で生きていくこと、と言えます。そのためには、自文化への理解、他文化への理解、コミュニケーションの知識やスキル、など必要なことが様々あります。国境を越えた人の行き来が普通になっている中、とても大切な考え方になっています。
ーーー具体的にどんなところが魅力なのでしょうか?
安先生 普段当たり前すぎて意識していない自文化や、様々な他文化を理解していくことは単純に楽しいですよ。色々な人と関わったり、色々なところに行ったりしながら学べますし。そうやって、様々な人との関わりや社会のことを学び考えるることで、共生する力を身に付けられます。
ーーー外国人との関り方について学べるということですか?
劉先生 外国人に限りませんよね。世代、ジェンダー、地域、隣にいる人は自分とは異なる背景を持っていますよ。ですから、多文化共生の知識やスキルを身に付けられると、将来何をするにしても自分の生活や人生を豊かにしてくれると思いますよ。
ーーー最後に受験生へのメッセージをお願いします。
奥山先生 留学生と関わったり海外に行ってみたりして、様々な文化を体験してみましょう。講義で学ぶ専門的な知識を踏まえてそうした体験を繰り返すことで、人や社会への理解がぐっと深まります。「多文化」について学んで、自分のこと、他者のこと、社会のこと、を深く理解していくのは、とても知的な刺激に満ちた経験ですよ。一歩踏み出す勇気を持ってみましょう。
安先生 「アンニョンハセヨ!最近、日本では様々な国の文化が人気です。皆さんの好きなものは何ですか?「好きこそものの上手なれ」という言葉があります。皆さんの好きなものを一緒に掘り下げてみませんか?きっと今まで気づかなかった風景が広がるはずです。多文化コミュニケーションコースで皆さんを待っています!」
劉先生 料理(ラフテー)、建築(赤瓦の屋根)、芸能(古典音楽)、祭り(旧正月)など、さまざまな面で中国文化が根付いており、それが沖縄独自の文化として発展しています。このような多文化共生の環境は、沖縄の魅力の一つであり、異なる文化を比較することで、自分の文化への理解がグッと深まります。言語や文学は、その文化を映し出す鏡。さあ、一緒に多文化の世界へ飛び込んでみませんか?沖国大日文で新しい発見が待っています!
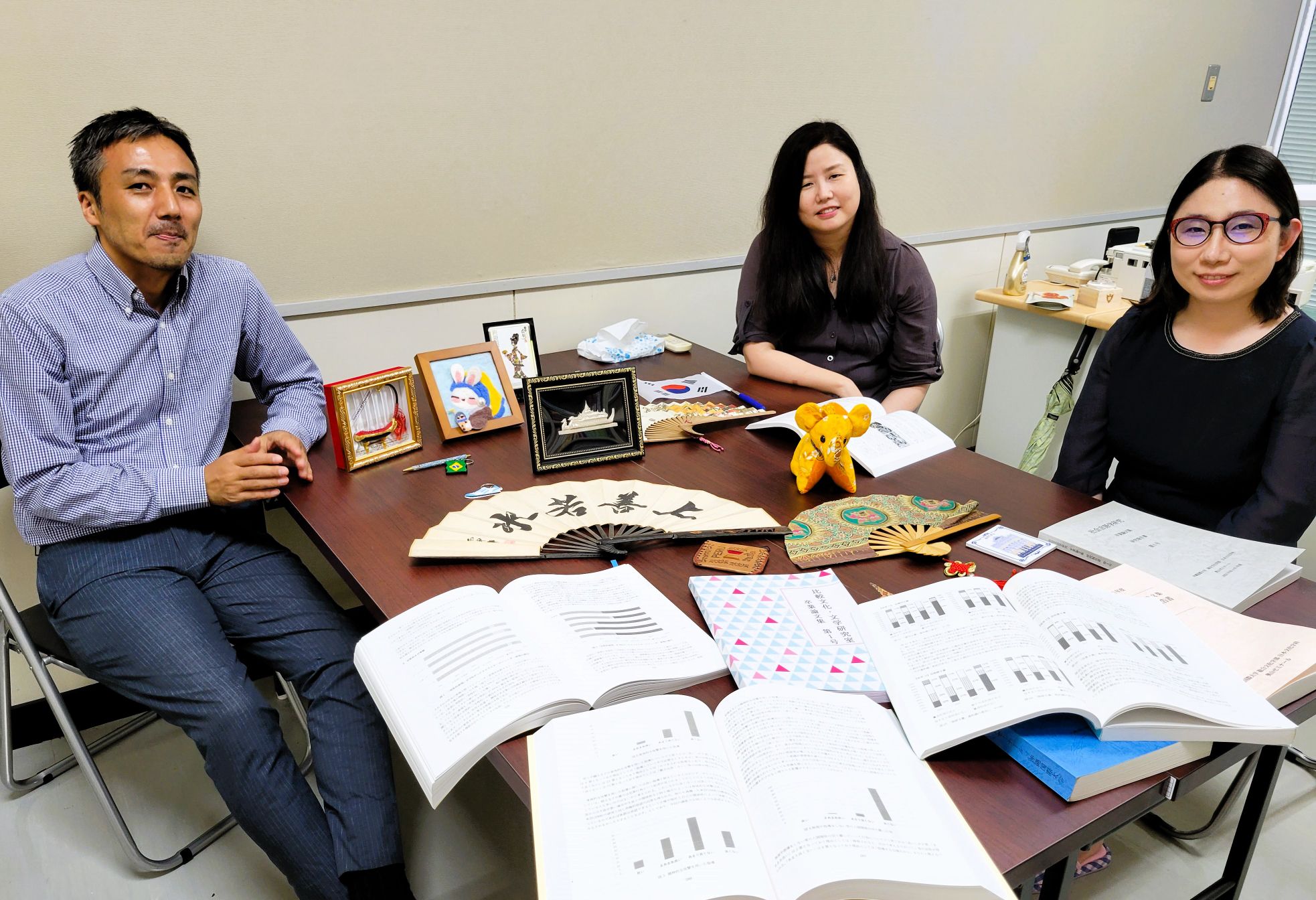
ーーー先生方、本日はありがとうございました。多文化間コミュニケーションコースのことがよくわかりました。受験生の皆さんもぜひ日本文化学科で一緒に多文化について学びましょう!

